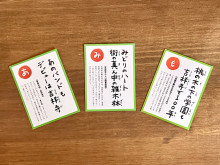企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁。以下AIデータ社)は、9月25日に農業界におけるAI活用とDX推進をテーマにした「AIエージェント×AI/DXフォーラム~農業」 を開催いたしました。 本フォーラムでは、日本の農業が直面する人手不足・属人化、技術継承の困難といった課題に対し、AIによる生産性の向上、ノウハウの継承、分断されたデータの統合活用など、持続可能な次世代型農業の構築に向けた多様な提案がされました。
開催レポートの詳細はこちら

AIエージェント×AI/DXフォーラム 農業
■セッション1 「世界のアグリテックに追随する一手、AIエージェント時代に日本の農業界が起死回生のAI高速道路に乗る唯一の方法は?」

AOSグループ代表 佐々木 隆仁
弊社佐々木より、日本農業が抱えるDX化の遅れや生産現場の属人化、技術継承の困難さを念頭に、生成AIとAIエージェントを活用した「高速道路モデル」の導入を提案しました。農家や自治体・企業が、AI活用のハードルを大幅に下げ、現場に最適な形で迅速に導入できる仕組みとしての構想を示し、特に、農業データとノウハウを集約・構造化し、AIが問いに応じてリアルタイムに判断支援を行うことで、生産性向上やリスク低減を実現する道筋を提示しました。「AI高速道路」モデルとは、段階的導入、テンプレート化、プロンプト支援を組み込んだ導入支援設計のことと説明。食料安全保障や農業競争力強化という観点から、国の戦略インフラとしてAI・DXを位置づける意義も強調しました。
■セッション2 「農業分野におけるデータ活用の促進に向けて」
光廣氏は、政策面から農業におけるデータ利活用の現状と課題、そして促進の方向性について語りました。農業基本計画や国の方針として、農業DXやスマート農業推進が掲げられており、その一環として、データプラットフォーム構築やデータ連携基盤の整備が急務であると説明。自治体・地方・農協など地域現場との連携強化、農業生産者のICTリテラシー向上支援、データの標準フォーマット整備やインセンティブ設計などの政策的取り組みについて具体的施策を説明。さらに、民間・研究機関との共創モデルを促進し、公共データ・センサー・気象・衛星データなど多種のデータを利活用する体制構築の必要性を訴えました。

農林水産省 大臣官房 政策課 技術政策室 課長補佐 光廣 政男 氏
■セッション3 「農業を次世代の成長産業に再設計、新規就農者でも高収益経営を可能にする『AI AgriSense on IDX』とは」

AIデータ株式会社 取締役CTO 志田 大輔
弊社志田より、新規就農者や中小農家でもAIを活用して高収益化を実現できるようなプラットフォーム「AI AgriSense on IDX」を紹介しました。このシステムは、農業に関わる各種データ(気象・土壌・作業記録・作付データなど)をIDX基盤に集約し、生成AIで可視化・判断支援を行う仕組みです。熟練農家の勘や経験もノウハウ化してAIに取り込むことで、属人的な判断を標準化。テンプレートやプロンプト支援など業界向けモジュールを備え、初めて農業に携わる方でも直感的に活用できる環境を整えています。事例を交えて、AIによる施肥・病害予測・収量分析などの活用例が紹介され、「農業DXへの橋渡し」としての役割を強調しました。
■セッション4 「農業データ連携基盤WAGRIの挑戦」
鶴氏は、農業データ連携基盤「WAGRI」の運営と実践的な課題を説明されました。WAGRIは、全国の農業関連データを集めるプラットフォームで、農業基本計画におけるデータ駆動型農業の中核インフラと位置付けられています。講演では、センサーデータ、営農記録、気象・衛星データなどを連携し、利活用可能な形に整備する仕組みを紹介。また、民間企業やアプリケーションとの連携事例から、現場でのAI導入や分析活用の可能性と課題を提示。さらに、データ標準化・可搬性・データ提供ルール整備など、行政・研究・産業をまたぐ連携型体制構築の重要性も強調されました。

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 基盤技術研究本部 農業情報研究センター WAGRI推進室 非常勤顧問 鶴 薫 氏
■セッション5 「分断されたデータを価値に変えるDX-BPOとAI AgriSense連携の処方箋」

PLANT DATA株式会社 代表取締役CEO 北川 寛人 氏
北川氏は、農業データがあちこちに分断されてしまっている現状を問題視し、それを価値に変える手段としてDXBPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)とAI AgriSenseの連携モデルを提案しました。具体的には、営農記録・圃場データ・流通データなどをDXBPO事業者が統合・整形し、AIによる判断支援に繋げるスキームを紹介。データ精度・ICTリテラシー・インフラ制約などの課題に対して、部分的なアウトソーシングとAI補完を組み合わせる処方箋を示しました。農業のバリューチェーン全体を視野に入れた連携型DXモデルの可能性を語りました。
■セッション6 「農業DXでサスティナブル&スマート水田」
下村氏は、水田農業におけるDXの最前線を語り、環境負荷抑制と生産性向上を両立させるスマート水田構想を紹介しました。ロボットやIoT、AIを活用し、水管理・施肥制御・収量予測などをリアルタイムにモニタリング・制御できる環境を構築。従来の土壌・気象制約をAIで補正し、持続可能な農法へと転換を図る事例を提示しました。減反政策から増産への流れの中で、質を保ちつつ収量拡大を目指すための技術的アプローチが語られ、未来の水田経営のビジョンを提案されました。

株式会社笑農和 代表取締役 下村 豪徳 氏
【AIデータ株式会社について】
名 称:AIデータ株式会社 代表者:佐々木 隆仁
設 立:2015年4月 所在地:東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
資本金:1億円(資本準備金15億2500万円) URL: https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。9,000社以上の企業、90万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワード16年連続で販売本数1位を獲得しています。
データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明(TM)』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。